セミナーの様子COMMEMTS
受講生の感想(2024年度)
【②「討議民主主義と合意形成」クラス 】
セッション1 無作為抽出市民による討議:社会実験から制度化の動向
- グループでの感想をまとめる。選挙しか政治に参加できず、さらに現在のような政治不信の時代に、政治への関わりを持てる場を設けることは政治への関心意欲を高める。学習前の感情的な「世論(せろん)」がよく考え抜かれた「輿論(よろん)」へなるなど、実際に話し合うことで地域の課題についての意識が変わった事例があるので、今回の講義には納得した。小学校の義務教育段階からこのような取り組みを行うべき。どのような専門家を呼ぶかで、一歩間違うと行政の意図を押し付ける儀式の場になる恐れがある。参加者の批判的思考(クリティカルシンキング)を学ぶことを小学校から始めるとよい。
- 典型的なNIMBY問題に対し、思考停止しないようにしたい思った。
- エンゲージメント調査など、HR部門主導の定点調査が浸透しつつあるが、討議型世論調査の応用も今後浸透するような気がした。また、この種の討議を経ることで、どのような技術革新が重要なのかについての理解を深められることを体感できたのはとても良かった。
- 講義あり、受講者同士での議論ありであっという間の2時間でした。「民主主義と合意形成」という今まで考えたことのない分野ではありましたが、講義、疑似DP体験ともにとても興味深かったです。参考文献をたくさん提供いただいたので、目を通してみようと思います。
- 討議型世論調査、恥ずかしながらまったく存じ上げておらず、それ故に大変興味深く、おもしろいお話や体験ばかりでした。
- 素晴らしい合意形成手法であると感じましたが、事前に与えられる情報、専門家の特徴・考え、ファシリテーターの能力に左右されてしまう部分もあり、如何に公平性や無作為性を担保するかが重要であると思いました。情報や議論をコントロールすべきでないか、ある程度コントロールするべきか、意見が分かれる点だと思います。
- “事前に情報を与えられ議論し判断する”という方法は、選挙などにも有効なのではないかと思いました。有権者は候補者のことをもっとよく知り検討の上、投票すべきであり、そのための材料(情報)を与えられるべきかと。現在も様々な方法で情報が提供されてはいますが十分でなく、偏りがあるように思います。(現在は、中身より知名度、人気が先行しているのでは)
- 今回のセミナーを通じて、無知の怖さを再認識しました。事前情報が与えられることは重要ですが、一時的な付け焼き刃な知識では難しいテーマを取り扱うことは難しく、社会的な問題に対して日常的に関心を持ち、自分なりの考えを持っておくことが大切であると学びました。
- 討議型世論調査は、結論をだすツールでなく、議論する・知るツールとして大変有効であると思いました。
- 国際的・国家的な課題を対象としたテーマであったが、一般市民の関心を高めて参加を促し、意見を効果的に拾い上げることが出来るという意味でとても興味深い内容であった。専門家の選定方法や参加者にとっての利点など、今後深く知りたい内容も多かった。
- 熟議制というしくみをどのように社会実装していくのか、が興味深かった。無作為抽出された市民がどの位の意識レベルで討議に参加するか、ファシリテーターの中立性の担保、回答する専門家の人選の基準等々、課題は多い。
- そもそも危険な物質の廃棄場所に関して、進んで合意を得るのは難しいと感じた。安全なデータの開示を繰り返す、あるいは放射性物質の危険性を軽減する技術を向上させ、市民の合意を得ていくプロセスが重要と思う。
- 「熟議」→専門家からの回答という合意形成の手法は実務でも取り込んでみたいと思う。
- 「自由な討議の場をつくる」、信頼できるサード・パーティ、DPのファシリテーションの可能性について、イメージを広げることができました。ありがとうございました。
- 今回のセミナーで体験したDPの課題として「討論時間不足」「専門家との議論不足」「少人数討論による意見誘導(価値観の偏り)」を感じました。このあたりの課題はITを活用した大規模オンライン会議(非同期)で解決できそうな気もします。
- 行政を円滑に進めたい行政側と地域課題題に関心が低い市民が、それぞれ「専門家信仰」をベースに、行政の意図をソフトに納得させたり、不満のガス抜きになったりしないでしょうか。
(講師からのコメント:行政の設置した場で用いると、行政の都合の良い意見のみを政策に取り入れる、あらかじめ決めたことを押し付けることは十分あり得ます。実際、自由参加の場では、一部の声の大きい人、もしくはグループの声を除外することになるという点にメリットを感じる担当者もいます。) - 同じ検討メンバ−でファシリテーターだけを複数回変えた場合、偏りの問題が是正されていくようなことが期待できるでしょいうか。また、実際そのような取り組み、実験は行われているでしょうか。
(講師からのコメント:グループを何度も組み替える方法は、計画細胞、ワールドカフェというやり方で採用されています。発言回数が均等になったり、特定の誰かの意見の影響がなくなったりするといわれています。) - 国民の代表となる有識者等で結論を出し、それを判断基準にして国が強制的に決めるような合意形成プロセスではダメなのでしょうか(弱者=一般国民の利益を保護し、議論の過程を透明化するような検討プロセスを導入することで、権力者(代表者、国など)の都合の良い方向に行かないような仕組みづくりによって制御する)。同じテーマを題材に、他の合意形成プロセスで得られた結果との比較などはあるでしょうか?
(講師からのコメント:同じ結論になる場合も、異なる結論になる場合もありえると思います。専門家にも無意識の認知バイアスがあることが指摘されています。これについては、2回目の授業ではなします。) - 原発という対立が起きやすい問題でDPによってどのように合意形成できたのか、疑問をもちました。
(講師からのコメント:全国の有権者から無策抽出した市民による討議で、立地予定地周辺の住民ではありません。) - 専門家への質問が討議終了後である理由は「情報の平等性」のためでしょうか。
(講師からのコメント:専門家の意見の影響を少なくし、独自の意見を形成し、専門家の話を深く理解するためです。) - 多様な価値観の人と討論することが重要だと思うがグループ分けはどのように行うのでしょうか。
(講師からのコメント:無作為に振り分けます。) - DPは合意形成とは独立であるべきかもしれないと思います。
(講師からのコメント:DPの設計者は、そのように考えています。) - ITを活用した大規模オンライン会議(非同期)で解決できそうな気もします。
(講師からのコメント:参考になります。) - 国内でそれほど普及していなことに疑問を持ちました。
(講師からのコメント:議員と有識者会議があれば十分と考えているからではないかと思います。) - 最後にお話のあった「政府は学術会議での意見を無視した」という点が問題・課題であり、政治力の強さは本調査の浸透を妨げている要因のひとつではないかと思いました。
(講師からのコメント:政策形成のどの段階に用いるかによって様々な使い方があります。二回目の講義で紹介します。) - ファシリテーターの能力に左右されてしまう部分もあり、如何に公平性や無作為性を担保するかが重要であると思いました。
(講師からのコメント::計画細胞というやり方では、ファシリテーターがいません。議論するのに、必ずしも必要ないことになります。) - 情報や議論をコントロールすべきでないか、ある程度コントロールするべきか、意見が分かれる点だと思います。
(講師からのコメント:コミュニケーションの基本ルールがあります。それだけ、守られればよいというのが基本的な考え方です。) - 選挙などにも有効なのではないでしょうか。
(講師からのコメント:米国では、大統領選挙の際に用いられたことがあります。) - 代表的な複数の市民によって調整された生成AIなどの活用などは実験されそうなどありますでしょうか。
(講師からのコメント:討議支援のためのICT活用は活発に行われているようです。) - 小グループ構成も、基本はランダムが良いと思える一方、討議テーマに対して知識差が大きすぎる場合には工夫の余地があるのではないかと思えました。
(講師からのコメント:もともとは、議会(代表民主制)、直接投票(直接民主制)の機能不全に対する対策として考えられているので、無作為抽出しているのだと思います。) - 質問を投げかける「専門家」の選定方法の実態を知りたいです。
(講師からのコメント:政策案件に中立なステアリングコミッティーを組織し、考えうる論点について洗い出し、立場の異なる専門家を特定していきます。ある手法では、呼ぶべき専門家自体を無作為抽出した市民が選ぶこともできます。専門家には、利害関係者も含まれます。裁判の証人に相当します。) - 参加者への報酬も妥当な費用感なのか、参加するに値する金額を整理することも有効ではないかと思います。
(講師からのコメント:米国では、最低賃金をめやすのすることもあるようです。カナダ、EUでは無料のことも多いい用です。どちらも、参加者の偏りに大きな差はないようです。) - 討議型世論調査はあくまで世論調査だと思うので、得られた結果をどう活用するのか、活用できるのかがよくわからなかったです。
(講師からのコメント:結果の活用については、2回目の講義で話します。) - 賛成派・反対派・中立などの割合が討議等を通じてどう変化するかが把握できる討議型世論調査の実施から、合意形成や政策決定に至るまでプロセスが気になります。
(講師からのコメント:エネルギーについてのDP事例の分析で、意見変容についてて、次の本に書かれています。「学ぶ、考える、話しあう」討論型世論調査―議論の新しい仕組み― (ソトコト新書) 新書) - 今回は高い放射性廃棄物に関するトピックスでしたが、他にはどんな事例があるでしょうか。
(講師からのコメント:日本では、年金、道州制、自治体総合計画などがあります。海外では、外交、憲法改正、中絶、などさまざまです。) - ファシリテーターの教育、スキルアップはどのように行うのでしょうか。
(講師からのコメント:DPに関していえば、簡単なトレーニング数時間程度を行います。ファシリテーターの教育、スキルアップはどのように行うのでしょうか。
(講師からのコメント:DPに関していえば、簡単なトレーニング数時間程度を行います。) - 「総論賛成、各論反対」という課題への対処はどのように行われていますでしょうか。
(講師からのコメント:政策レベルの決定と、個別立地を巡る利害関係者の合意とはわけて考える必要があると思います。)
- また今回の事例のステークホルダーとして、原子力委員会と学術会議の対立構造がありましたが、学術会議の意見を無視したという結果について、どんな仕掛け・デザインをすればよかったのでしょうか。
(講師からのコメント:意思決定との接続については、第二回の講義で触れたいと思います。)
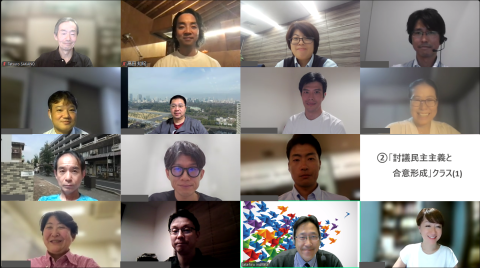
(2024年度②「討議民主主義と合意形成」クラス、セッション1 にて)
- 「相手を尊重する」「お互い協力関係にあることを認識する」等、一般的な規範として言われていることが、ゲーム理論等から理論的に導出できることがわかり、納得感があった。
- 自身は、現在のまちづくり活動の現場において、合意形成に直面し、対応してきたが、本講義において、その学問的・歴史的背景を学べるのは、非常に有意義な時間となっている。今回は、景観に関するテーマを扱ったが、あらためて、この問題の難題さを感じるとともに、市民の行動の重要性を認識するとともに、市民行動の可視化、体系化が必用になっていると感じた。
- 今回テーマで取り上げた問題に関して、大藤判決を聞いた上で議論をすると、かなりバイアスがかかった議論になったように感じた。最初のステップでは判決内容を聞かないで議論しても良かったかもしれない。
- 国立景観訴訟の事例、仕事として環境影響評価に携わっており、その中の評価項目のひとつとして「景観」があるため、身近な課題・問題として考えさせていただきました。環境アセスでは、景観はフォトモンタージュ法により予測し、関係自治体の景観計画等に準じて評価を行うことが一般的ですが、個人の主観性に左右される部分が大きいため、曖昧な結論となります。賛成と反対に分かれますし、どちらの意見も正しく、否定されるものではありません。
- 私個人としては、宮岡判決は、あえて住民側に寄り添った判決のように感じました(社会への問題提起ではないか)。地域住民が守ってきたもの、という点は理解できる部分ではありますが、公的な裁判の中で主張する内容としては根拠や理屈に欠けるものかと。
- 今回のセッションにてお話のあった「景観問題は、まちづくり委員会などにおいて3、4割は自己解決が図られており、裁判まで行われていない」ということに強く納得しました。問題・テーマによっては、法に委ねるのではなく、コミュニケーションをとり、長期的な関係性の構築により合意形成を図ることが大切であることを学びました。
- 前回の講義で出た質問に対して、「今回の講義で解説する」と話があったが、講義中に回答の解説がなされていると把握できませんでした(理解不足でしたら申し訳ないです)。せっかく質問に対してwordでコメントをいただけるのであれば、文字で回答をいただけると助かります。
- 最初に前回の問いに対するフィードバックを行っていただけたこと、また個別のセッション・サマリーの原稿に対して丁寧なご回答をいただけたことが非常にありがたかった。これにより振り返りも可能となり、より理解が深まったと思う。
- 制度下の知識(近代的な知識、専門的な知識)によって、日常生活に求められる生活ベースの判断力(規範性や誠実性)が削がれていったとする指摘は、個人的にとても腹落ちするものでした。
- 今回のセッションでは冒頭に、宮岡判決VS大藤判決という議論をおこなったが、法的な視点は合意形成において重要な前提知識であると感じた一方で、そもそも住民訴訟に発展する際の住民と企業そして行政がどの様な話し合いがなされたのか、この点を検討していくことも合意形成を学ぶ上では重要だと思っています。このケースでは、住民と企業の争いがまとまらず最終的に司法の場に持ち込まれたので、合意形成がなされなかったケースでしょう。よって、どのような対立やそれを埋めるコミュニケーションの程度など、こうした点も触れられるとより良い学びになると思います。
- 住民運動や市民運動や中間団体が衰退している。そもそも住民主体の地域づくりはどうしたらよいのか。話合いよりも、判例あるいは立法による「法化」が進んでいる。話合いのモチベーションはどうなるのか。裁判外紛争問題解決(ADR)など、話合い相手が行政機関となる。合意形成そのものの経験不足、忌避感も少なくないように見える。
- 10/16の①初回導入セッションにて、坂野先生が「熟議民主主義のモデルはたくさんある」とおっしゃっていたと思うのですが、②セッション内ではあまり言及されていなかったので、代表的なモデル名称や参考文献を教えて頂けると有難いです。
- 坂野先生の講義内容はボリュームが大きいので2回では足りないと思いました。講義資料の最初で講義概略を説明頂いたのですが、この概略部分をもう少し拡充頂けると有難かったです(時間不足の前提)。
- 10/23のDPとの繋がりが知りたかったです。(集団的意思決定(合意形成の場)におけるDPの役割、位置づけ)
- 今回の例題「国立のマンション建設により景観関する討議内容」では前回と違い法律的な取り決めに基づき、判断をしていた自分自身に少し驚きました。今迄は、感情を重視するところ多々あり、論理的な資料提供が豊富にあると、以外に人は冷静になれるのではないかと感もじました。
- 坂野先生がファシリテーターの合場、今までの合意形成の場で、自信の意見を討議中、討議 後でも発言をされたことはあったのか、その場合はどのような考えで発言されたのかお聞きしたいと思いました。
- 明和地所の事例と反対に、合意形成の場をうまく作れた事例があれば知りたい。
(講師からのコメント:景観紛争事例ではありませんが、授業で少し触れた田園調布の街づ切事例や、狛江市の調整会の制度は、事前協議の仕組みとして参考になります。) - 住民運動や市民運動や中間団体が衰退している。そもそも住民主体の地域づくりはどうしたらよいのか。
(講師からのコメント:狛江市の調整や、まちづくり提案制度は、まちづくりの参加制度としてて参考になります。) - そもそも工事中の事案には適用されない条例(20m以上の建築物に対する)であれば、制定する前にわかっていたと思われるが、このような決定に至ったプロセスに問題があったと感じる。回避する適切な方法はあったのか。
(講師からのコメント:行政の対応が不適切であったと私も思います。そのようなことを回避するための制度として、狛江市の調整会の制度が参考になります。) - このケースでは、住民と企業の争いがまとまらず最終的に司法の場に持ち込まれたので、合意形成がなされなかったケースでしょう。よって、どのような対立やそれを埋めるコミュニケーションの程度など、こうした点も触れられるとより良い学びになると思います。
(講師からのコメント:宮岡判決の論理は、既存の方には裏付けられていないので、法的に裏付けられていない民体民の合意の条件を公共性という観点から考えるうえで参考になると考え紹介しました。事例は、調べる必要はあるのですが、事前に合意されたケースでも基本的には同じ論理が適用できると考えています。) - 話合いよりも、判例あるいは立法による「法化」が進んでいる。話合いのモチベーションはどうなるのか。裁判外紛争問題解決(ADR)など、話合い相手が行政機関となる。合意形成そのものの経験不足、忌避感も少なくないように見える。
(講師からのコメント:法律は、交渉コストを下げる効果があります。所有権を定めた民法があるから市場取引でパレート最適が達成されます。ですので、両者は、車の両輪のようなものです。) - 今回のセッションにてお話のあった「景観問題は、まちづくり委員会などにおいて3、4割は自己解決が図られており、裁判まで行われていない」ということに強く納得しました。問題・テーマによっては、法に委ねるのではなく、コミュニケーションをとり、長期的な関係性の構築により合意形成を図ることが大切であることを学びました。
(講師からのコメント:法律は、交渉コストを下げる効果があります。所有権を定めた民法があるから市場取引でパレート最適が達成されます。ですので、両者は、車の両輪のようなものです。コミュニティが機能すれば、法の規律密度は低くすることができます。) - ここに“時間軸”を導入し、その期間内に代案が出てこない場合(単に批判するだけではNO!)、原案を進めるといったアプローチはできないのか?)。
(講師からのコメント:時間フレームを誰がどのように決めるかは、一般的にはアジェンダセッティングの問題になるかと思います。アジェンダセッティングに、無作為抽出市民が入ることは、規範的には望ましいと思われますが、ベルギーの事例を除いて行われていないのが現実だと思います。) - 相互依存関係性を参加者全員で共有し、長期的な関係性を持つことが合意形成の場で重要であることを学んだが、その対象とする範囲や時間軸をあらかじめ明確にしないと、適切な合意形成がなされないように感じた。この点はあらゆる事業において言えることと思うが、この方法論について、今後のクラスにおいてより深く学びたいと思う。
(講師からのコメント:時間フレームを誰がどのように決めるかは、一般的にはアジェンダセッティングの問題になるかと思います。アジェンダセッティングに、無作為抽出市民が入ることは、規範的には望ましいと思われますが、ベルギーの事例を除いて行われていないのが現実だと思います。また、アジェンダセッティングや交渉参加者の選択を含めて、どのように交渉の場をセットするかは、セットされた後に、交渉をどう進めるかと同じ程度重要だと思います。講義の最後に整理した、6原則はそのためのものと考えています。) - 互換的利害関係を学び「地域自治(地域コミュニティ)」の重要性を感じました。互換的利害関係というのは自然発生するものというより地域で創り出していくもので、それが地域の特性や価値へと繋がるものだと思う。この互換的利害関係を生み出す地域コミュニティの創り方や広げ方(互換的利害関係を創ることの正当性)が重要だと思いました。そして、そのようなコミュニティ構造が「あるべき合意形成の場」となっていくのではと思いました。
(講師からのコメント:同意見です。) - いわゆるTFT(tit-for-tat)戦略は、感覚的ですが親から子への教育で少なくとも僕たち親世代は教わり教えているんじゃないかと感じました。初手で他者に迷惑をかけるな。もし迷惑な人がいたらフリーライドされるから報復しろ。ただし反省したらノーサイド(罪を憎んで人を憎まず)。
(講師からのコメント:TIT戦略が社会に共有されるのは、個人個人の自覚や選択ではなく、進化的に社会が獲得してきたものだと思います。それを、ゲーム理論の枠組みで説明したり、社会心理学的に確かめているという形で、後追い的に説明したり理解しているのだと思います。しかし、従来の社会科学は、利己主義を前提にしたり、利他主義を規範的に押し付けようとしてきたことを考えると、社会制度を考えるうえで、自由度が増してきているのだと思います。) - ゲーム理論や経済学理論の「利得の最大化」という価値基準だけでなく、「幸福」「安全」「安心」「正義」など抽象的な概念をどうやって取り込むことができるのか、という疑問がある。
(講師からのコメント:パレート最適は、社会包摂性のみに対応し、いわゆる分配公正という正義と密接な関係のある問題には適用できません。その他の幸福、安全、安心は、リスク判断の事例で紹介したように、社会的に(コミュニケーションを通じて)構築されるものなので、ゲーム理論では扱えない問題だと思います。ですので、ハバーマスについても触れました。一方、ハバーマスらの議論には、ゲーム理論があつかうようなインセンティブが抜け落ちているので、両者を補完的に用いることが必要だとおもっています。) - 公共性を重視した場合の合意形成の基本的な考え方に対して、人情、心情も織り交ぜながら合意に導くことは、可能かどうか探究してみたいです。
(講師からのコメント:人情、信条にとって大切にすべきことは、存在感情だと考えています。相手や自分の存在が認められている感覚が持てることが、ハバーマスの誠実性がコミュニケーションで実現する基本的条件だと考えています。) - 双方にとって情報に非対称性が存在し、それをお互い相手方に曝け出すことは基本ない。
(講師からのコメント:情報の非対称性があることと、truth tellinhする誘因が働くかは別問題です。制度設計上は、前者は必ずしも必要なく、後者が重要だと考えます。)
- 初回導入セッションにて、坂野先生が「熟議民主主義のモデルはたくさんある」とおっしゃっていたと思うのですが、②セッション内ではあまり言及されていなかったので、代表的なモデル名称や参考文献を教えて頂けると有難いです。
(講師からのコメント:討議民主主義の挑戦,篠原一編,岩波書店。および、文献リストのDを参照ください。) - 前回の講義で出た質問に対して、「今回の講義で解説する」と話があったが、講義中に回答の解説がなされていると把握できませんでした(理解不足でしたら申し訳ないです)。
(講師からのコメント:時間の都合でしっかり説明せずにいました。すみません。熟議の結果が公的意思決定に結びつく仕方については、Citizen AssemblyとCitizen Initiativeが制度的にはしっかりしていると思います。文献リストのAにある論文をお読みください。A3 多様な政治体制下における熟議民主主義の展開 計画行政 第45巻4号、A5今ミニ・パブリックスを考える 都市問題 2024年1月号(これは、新しくアップロードします)。) - エリノア・オストロムは、市民の行動で、社会課題解決が図れることを主張したとのお話に関心がある。彼女は水利などの観点から、コモンズを研究し、女性初のノーベル経済学賞を受賞したことは知っているが、あらためて調べてみたい。
(講師からのコメント:Governing the Commons: the Evolution of Institutions for Collective Action, (Cambridge University Press, 1990)は、理論編がわかりやすく書かれています。訳本もあるようです。『コモンズのガバナンス―人びとの協働と制度の進化―』 原田禎夫・齋藤暖生・嶋田大作 訳、晃洋書房 2022年)
- 坂野先生の講義内容はボリュームが大きいので2回では足りないと思いました。
(講師からのコメント:2回の講義で何を話すか、初回の皆さんの反応を見て2回目を決めているので、整理しきれず申し訳ありませんでした。次回以降、参考にして工夫してみます。)
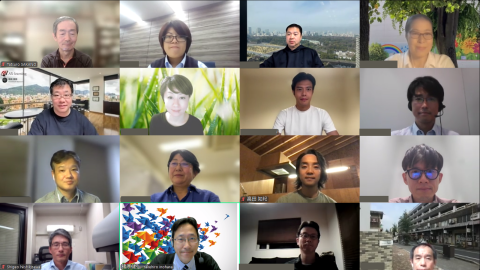
(2024年度②「討議民主主義と合意形成」クラス、セッション2 にて)